窓フィルムで遮熱・断熱効果UP!室温-5℃&電気代20%節約も
- トカクサポート
- 2月23日
- 読了時間: 19分

▶︎1. 窓の遮熱フィルムとは?

1.1 遮熱フィルムの基本的な仕組み
遮熱フィルムは、窓ガラスに貼ることで太陽の熱をカットし、室内の温度上昇を抑えるアイテムです。特に夏場の暑さ対策として人気があり、エアコンの効率アップや紫外線対策にも効果的です。
遮熱フィルムの仕組みは、主に 「赤外線の反射・吸収」 によって成り立っています。フィルムには特殊な金属やセラミックがコーティングされており、以下のような働きをします。
まず、赤外線を反射するタイプの遮熱フィルムは、太陽光の熱エネルギーを窓の外に跳ね返し、室内の温度上昇を防ぎます。特に日差しが強い場所や、大きな窓のある部屋に適しています。
一方、赤外線を吸収するタイプの遮熱フィルムは、窓ガラス自体が熱を吸収し、室内に伝わる熱の量を減らす仕組みです。外からの熱を抑えつつ、ある程度の明るさを確保したい場合におすすめです。
また、多くの遮熱フィルムは 紫外線カット効果 も備えています。99%以上のUVカット性能を持つ製品も多く、家具や床の日焼け防止、肌へのダメージ軽減にも役立ちます。
このように、遮熱フィルムは赤外線の反射・吸収を活用しながら、室内の温度を快適に保つための工夫が施されています。
1.2 遮熱フィルムと断熱フィルムの違い
遮熱フィルムと断熱フィルムは、どちらも窓に貼ることで快適な室温を保つアイテムですが、目的が異なります。
遮熱フィルムは、太陽光の熱をカットし、室温の上昇を防ぐのが主な役割です。特に夏場に活躍し、エアコンの効率を向上させて冷房効果を高めます。
一方、断熱フィルムは、室内の暖かい空気を外に逃がさないのが特徴です。冬の寒さ対策として効果的で、暖房の熱をしっかりと室内に留める役割を果たします。
それぞれの違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
遮熱フィルム → 夏向け(太陽熱を反射・吸収して室温上昇を防ぐ)
断熱フィルム → 冬向け(室内の暖気を外に逃がさず、保温効果を高める)
どちらを選ぶべきかは、住んでいる地域や季節によって異なります。暑さ対策が必要なら遮熱フィルム、寒さ対策が重要なら断熱フィルムが適しています。
なお、一部のフィルムは 遮熱と断熱の両方の効果を兼ね備えているタイプ もあります。年間を通して快適な室温を保ちたい方は、オールシーズン対応のフィルムを選ぶのもおすすめです。
1.3 遮熱フィルムのメリット・デメリット
遮熱フィルムには多くのメリットがありますが、デメリットもあります。
ここでは、それぞれのポイントを詳しく解説します。
遮熱フィルムのメリット
室温の上昇を防ぎ、快適に過ごせる
太陽の熱を反射・吸収することで、室内温度の上昇を抑え、夏場も快適に過ごせます。
エアコンの効率が上がり、電気代を節約できる
遮熱効果によって冷房の効きがよくなり、エアコンの使用量を減らせるので節電につながります。
紫外線をカットし、家具や床の日焼けを防げる
99%以上のUVカット性能を持つフィルムが多く、室内のインテリアや肌を紫外線から守ります。
目隠し効果があるフィルムなら、プライバシー保護も可能
ミラータイプやスモークタイプのフィルムなら、外からの視線を遮る効果も期待できます。
遮熱フィルムのデメリット
冬場は室内の暖気も逃げやすい
遮熱フィルムは熱を反射するため、冬場は暖房の熱も外に逃がしやすくなります。冬の寒さが厳しい地域では、断熱フィルムと併用するのがおすすめです。
フィルムの種類によっては、部屋が暗く感じることがある
反射率の高いフィルムを選ぶと、日光の明るさが抑えられ、部屋が暗く感じる場合があります。明るさを確保したい場合は、可視光透過率の高いフィルム を選びましょう。
貼り方によっては気泡やシワができることも
自分で貼る場合、うまく施工しないと気泡やシワが入り、仕上がりが悪くなることがあります。初めての方は、プロに施工を依頼すると安心です。
このように、遮熱フィルムには 快適な室温維持や電気代の節約 などのメリットがたくさんあります。ただし、フィルムの種類や貼り方によってはデメリットもあるため、自分の目的に合ったフィルムを選ぶことが大切です。
▶︎2. 窓に貼る遮熱フィルムの効果と特徴

2.1 室内温度の低下効果はどのくらい?
遮熱フィルムを貼ることで、室内温度を2〜5℃ほど下げることができます。特に夏場の強い日差しが差し込む部屋では、効果をより実感しやすいです。
遮熱フィルムの温度低下効果は、フィルムの種類や窓の向きによって変わります。たとえば、南向きや西向きの窓は日差しが強いため、遮熱フィルムを貼ることでより大きな効果を発揮します。
また、室温の低下効果は フィルムの遮熱率 にも影響されます。遮熱率が高いフィルムほど、熱の侵入を防ぎ、快適な室温を保ちやすくなります。
遮熱フィルムの導入前後での温度差(例)
遮熱フィルムなし → 室温30℃
遮熱フィルムあり → 室温25~28℃
窓からの熱をしっかりカットすることで、室温上昇を防ぎ、快適な空間を作れるのが大きなメリットです。
2.2 UVカット効果で日焼け対策もバッチリ
遮熱フィルムの多くは、紫外線(UV)を99%以上カットする効果があります。紫外線は、肌の日焼けだけでなく、家具や床の色あせの原因にもなるため、UVカット効果のあるフィルムを貼ることで大切なインテリアを守ることができます。
紫外線は年間を通して降り注いでおり、特に南向き・西向きの窓は紫外線量が多くなります。そのため、UVカット機能付きの遮熱フィルムを活用することで、以下のようなメリットがあります。
UVカットフィルムの主なメリット
肌の日焼けやシミ・そばかすの予防
窓越しの紫外線も肌に影響を与えるため、室内にいても日焼けすることがあります。UVカットフィルムを貼ることで、室内にいても紫外線対策ができます。
家具や床の色あせ防止
フローリングやカーテン、ソファなどは、紫外線によるダメージを受けやすく、色あせが進む原因になります。遮熱フィルムを貼ることで、これらの劣化を防ぐことができます。
赤ちゃんやペットの健康対策
紫外線は人間だけでなく、ペットの皮膚にも影響を与えることがあります。特に日当たりのいい場所で過ごすことが多い場合、UVカットフィルムが役立ちます。
このように、遮熱フィルムを貼ることで 紫外線対策も同時にできるため、家族みんなが快適に過ごせる環境を作ることができます。
2.3 エアコンの効率アップで電気代を節約
遮熱フィルムを貼ると、エアコンの負担が減り、電気代を約10~20%節約できると言われています。窓から入ってくる熱をカットすることで、室温が上がりにくくなり、エアコンの稼働時間を減らせるからです。
特に、エアコンの設定温度を1℃下げるだけでも約10%の節電効果があるとされており、遮熱フィルムを活用することでより効率よく冷房を使うことができます。
遮熱フィルムによる電気代節約の仕組み
窓からの熱の侵入を防ぐ → 室温上昇を抑え、エアコンの設定温度を低くできる
エアコンの稼働時間を短縮 → 冷房の使用時間が減り、電気代をカット
設定温度を1~2℃高めにできる → 体に優しく、環境にも配慮した節電が可能
例えば、冷房の設定温度を 27℃から28℃に上げるだけでも、年間で数千円の電気代節約 につながると言われています。また、エアコンの効きが良くなるため、部屋が涼しくなるまでの時間も短縮されます。
このように、遮熱フィルムは 「電気代節約」「環境への配慮」「冷房の効率アップ」 という3つのメリットを同時に得ることができます。
窓に遮熱フィルムを貼ることで、以下のような効果が得られます。
室内温度の低下(2~5℃の温度低下が期待できる)
UVカット効果(99%以上の紫外線をカットし、肌や家具を守る)
エアコンの効率アップ(電気代を約10~20%節約)
このように、遮熱フィルムは 夏の暑さ対策だけでなく、省エネや紫外線対策にも役立つアイテム です。
▶︎3. 窓に使う遮熱フィルムの種類と選び方

3.1 反射タイプと吸収タイプの違い
遮熱フィルムには「反射タイプ」と「吸収タイプ」の2種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。どちらを選ぶかによって、遮熱効果や室内の明るさが変わるため、目的に合わせて選ぶことが大切です。
反射タイプの特徴
反射タイプの遮熱フィルムは、ガラスの表面で太陽光を反射することで熱の侵入を防ぐのが特徴です。フィルムの表面に金属コーティングが施されており、ミラーのような見た目になります。
メリット
遮熱効果が高く、室温の上昇をしっかり防げる
昼間は外から室内が見えにくく、プライバシー保護効果もある
エアコンの効率を高め、省エネ効果が期待できる
デメリット
外側がミラーのように反射するため、景観に影響を与えることがある
夜は室内の光が反射して外から見えやすくなる場合がある
こんな人におすすめ
日当たりが強い部屋で、しっかり遮熱したい人
外からの視線を遮りたい人
吸収タイプの特徴
吸収タイプの遮熱フィルムは、ガラス自体が熱を吸収し、室内への熱の侵入を抑える仕組みです。
金属コーティングは施されておらず、透明または薄いスモーク調の見た目が特徴です。
メリット
透明度が高く、窓の外の景色を損なわない
ガラスの反射を抑え、自然な外観を保てる
反射タイプよりも夜の視界が良く、室内から外が見やすい
デメリット
遮熱効果は反射タイプよりもやや劣る
熱を吸収するため、ガラスの温度が高くなる場合がある
こんな人におすすめ
景観を重視し、透明感のあるフィルムを使いたい人
反射を抑えて、夜間も視界を確保したい人
反射タイプ・吸収タイプ、それぞれの特徴を理解し、自分の窓に合ったフィルムを選びましょう!
3.2 可視光透過率と遮熱効果の関係
遮熱フィルムを選ぶ際は「可視光透過率」にも注目しましょう。可視光透過率とは、フィルムを通してどれくらいの光が室内に入るかを示す数値で、数値が高いほど明るい室内になります。
可視光透過率の違いによる影響
高透過タイプ(可視光透過率70%以上)
室内の明るさを維持しながら、ある程度の遮熱効果を得られる
透明感が高く、オフィスや店舗に適している
遮熱効果はやや低め
標準タイプ(可視光透過率40~70%)
適度な明るさを確保しながら、遮熱効果を得られる
住宅やマンションで使いやすい
低透過タイプ(可視光透過率40%以下)
強い日差しをしっかりカットし、遮熱効果が高い
室内が暗くなる可能性があるため、窓の向きを考慮する必要がある
例えば、南向きや西向きの窓は日差しが強いため、可視光透過率の低いフィルムが効果的です。逆に、北向きの窓は光が少ないため、透過率の高いフィルムを選ぶことで明るさを確保できます。
3.3 窓の向きや用途別おすすめフィルム
窓の向きや用途によって、最適な遮熱フィルムの種類が異なります。
以下のポイントを参考に、適したフィルムを選びましょう。
窓の向き別のおすすめフィルム
南向きの窓
一日中日差しが強いため、高い遮熱効果が必要
反射タイプの遮熱フィルム(可視光透過率40%以下) がおすすめ
西向きの窓
夕方の西日が強く、室温が上がりやすい
遮熱性能が高く、紫外線カット効果のあるフィルムが最適
東向きの窓
朝日が入るが、午後は日差しが弱くなるため、適度な遮熱効果でOK
標準タイプの遮熱フィルム(可視光透過率40~70%) がおすすめ
北向きの窓
日差しが少ないため、遮熱よりも採光を重視
透明タイプの遮熱フィルム(可視光透過率70%以上) が適している
用途別のおすすめフィルム
リビングや寝室
室温を快適に保ち、明るさも確保したい
標準タイプの遮熱フィルム がおすすめ
オフィスや店舗
作業環境を快適にしつつ、外の景色も見えるようにしたい
高透過タイプの遮熱フィルム が最適
目隠しをしたい窓(浴室・トイレなど)
プライバシー保護を重視する場合は、ミラータイプやスモークタイプの遮熱フィルム を選ぶ
遮熱フィルムを選ぶ際は、以下のポイントを意識しましょう。
「反射タイプ」か「吸収タイプ」かを用途に応じて選ぶ
「可視光透過率」を考慮して、室内の明るさを調整する
「窓の向き」に合わせたフィルムを選ぶ
これらのポイントを押さえれば、最適な遮熱フィルムを選びやすくなります。
▶︎4. 遮熱フィルムの施工方法と注意点
4.1 DIYで貼る場合の手順とコツ
遮熱フィルムは自分で貼ることも可能ですが、きれいに仕上げるにはコツが必要です。特に大きな窓の場合は、気泡やシワが入りやすいため、丁寧な作業が求められます。ここでは、DIYで貼る際の手順とポイントを紹介します。
遮熱フィルムを貼る手順
窓ガラスをしっかり清掃する
ガラスの表面にホコリや油分が残っていると、フィルムが密着しにくくなります。
ガラスクリーナーや中性洗剤を使い、汚れをしっかり拭き取ります。
フィルムのサイズを測り、カットする
窓のサイズに合わせてフィルムをカットします。
貼る際に微調整できるよう、窓よりも 数センチ大きめ にカットしておくと安心です。
霧吹きで窓にたっぷり水を吹きかける
水を吹きかけることで、フィルムが滑りやすくなり、位置調整がしやすくなります。
水に少量の中性洗剤を混ぜると、より密着しやすくなります。
フィルムの剥離シートをはがし、窓に貼る
端からゆっくりと剥がしながら貼ることで、シワが入りにくくなります。
途中でフィルムが折れないよう注意しましょう。
ヘラを使って気泡を取り除く
フィルムの中央から外側に向かってヘラを動かし、空気と余分な水を押し出します。
強く押しすぎるとフィルムが破れることがあるため、力加減に注意しましょう。
余分なフィルムをカットし、仕上げる
カッターを使い、窓枠に沿って余分な部分をカットします。
仕上げに、乾いた布で軽く押さえて密着させます。
DIYで貼る際のポイント
気泡が入った場合は、針で小さな穴を開けて空気を抜くときれいに仕上がる
冬場は気温が低くフィルムが固くなりやすいため、室温が高めの日に施工するのがおすすめ
失敗しないために、最初は小さな窓で練習すると良い
DIYでの施工は、費用を抑えられるメリットがありますが、大きな窓や複雑な形の窓に貼る場合は、プロに依頼するのも選択肢のひとつです。
4.2 プロに依頼するメリット
遮熱フィルムを貼るのが不安な場合は、プロに施工を依頼するのもおすすめです。
特に、大きな窓や高所の窓の場合は、DIYでは難しいため、専門業者に頼むと安心です。
プロに依頼するメリット
仕上がりがきれいで耐久性が高い
プロの施工なら、気泡やシワがほとんどなく、美しく仕上がります。
施工技術によってフィルムの寿命も長くなるため、長期的に見ればコスパが良いです。
特殊な窓にも対応できる
すりガラスや曲面ガラスなど、DIYでは難しい窓にも施工が可能です。
窓の種類に合った最適なフィルムを提案してもらえます。
高所の窓でも安全に施工できる
高い位置にある窓は、自分で施工するのが危険です。
専門業者なら、専用の機材を使って安全に作業してもらえます。
保証が付く場合がある
業者によっては、施工後に剥がれたり気泡が入った場合の保証があることも。
もし不具合が発生した場合でも、対応してもらえるので安心です。
プロに依頼する際の費用相場
一般的な家庭の窓(1㎡あたり):5,000円~10,000円
大型窓や特殊ガラス:10,000円~20,000円
DIYよりもコストはかかりますが、仕上がりの美しさや耐久性を考えると、プロに依頼するのも良い選択肢 です。
4.3 施工後のメンテナンス方法
遮熱フィルムは、正しくメンテナンスすることで長持ちさせることができます。
施工後のケアをしっかり行い、フィルムの効果を維持しましょう。
施工後すぐの注意点
施工後すぐは、フィルムを触らない
貼った直後は、まだフィルムが完全に密着していません。
触ったり、強くこすったりすると剥がれの原因になるので注意しましょう。
水や気泡が残っていても、1週間ほどで消える
貼った直後に小さな気泡が見えることがありますが、時間が経てば自然に消えます。
無理に押し出さず、数日様子を見るのがポイントです。
普段の掃除方法
柔らかい布やスポンジで優しく拭く
硬いブラシやスクレーパーは、フィルムを傷つける可能性があるため使用しない。
中性洗剤を薄めた水で拭くのがベスト
アルコールや強い洗剤はフィルムを劣化させるため、使わないようにしましょう。
フィルムの寿命と交換時期
遮熱フィルムの寿命は 約5~10年 ですが、以下のような場合は交換を検討しましょう。
フィルムが剥がれてきた
変色やヒビ割れが目立つ
遮熱効果が弱くなったと感じる
正しいメンテナンスを行うことで、遮熱フィルムをより長く快適に使うことができます。
DIYでの施工は可能だが、コツが必要。初心者は小さな窓から挑戦するのがおすすめ。
プロに依頼すると、仕上がりがきれいで耐久性が高くなる。特に大きな窓や高所の窓には向いている。
施工後は適切なメンテナンスを行い、フィルムを長持ちさせることが大切。
▶︎5. 窓の遮熱フィルムに関するよくある質問
5.1 賃貸でも貼れるの?剥がせる?
賃貸でも貼れる遮熱フィルムは多くあり、原状回復が必要な場合でも剥がせるタイプを選べば問題ありません。
賃貸物件では、壁や窓に加工を施すことが制限されていることが多いため、フィルムを貼る際には「剥がせるタイプ」かどうかを確認することが大切です。
賃貸向けの遮熱フィルムの選び方
貼って剥がせる再剥離タイプを選ぶ
粘着剤が弱めで、剥がしても跡が残らないフィルムを選ぶと安心。
「賃貸OK」や「再剥離可能」と記載されたフィルムを選びましょう。
静電気タイプのフィルムを使う
粘着剤を使わず、静電気の力で窓に貼り付くタイプのフィルムもあります。
何度でも貼り直しができ、賃貸でも気軽に使えます。
退去時に綺麗に剥がせるかを事前にチェック
いきなり全面に貼るのではなく、端の目立たない部分で試してから貼ると安心。
長期間貼りっぱなしにすると、粘着が強くなって剥がしにくくなることがあるので注意しましょう。
剥がすときのコツ
ドライヤーで温めながら剥がすと、粘着力が弱まり、綺麗に剥がせる。
中性洗剤を薄めた水を吹きかけながら剥がすと、粘着剤が窓に残りにくい。
このように、賃貸でも遮熱フィルムを活用できます。原状回復が必要な場合は、剥がしやすいタイプを選びましょう!
5.2 遮熱フィルムで冬は寒くならない?
遮熱フィルムは熱を反射するため、冬場は室内の暖房熱も外に逃がしやすくなります。そのため、冬に寒くなる可能性はありますが、フィルムの種類を選ぶことで対策できます。
遮熱フィルムが冬に影響を与える理由
遮熱フィルムは、太陽からの熱だけでなく、室内の暖房熱も一部反射してしまいます。
そのため、冬の寒さが厳しい地域では、室温が下がると感じることがあるのです。
冬でも快適に使うためのポイント
低反射タイプのフィルムを選ぶ
反射タイプではなく、熱を適度に吸収する「吸収タイプ」のフィルムを選ぶと、室内の暖房熱を逃がしにくくなります。
断熱機能付きの遮熱フィルムを選ぶ
遮熱と断熱の両方の効果を持つフィルムなら、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせます。
「オールシーズン対応」と記載された製品を選ぶのがポイント。
冬場は厚手のカーテンや断熱シートと併用する
窓からの冷気を防ぐために、遮熱フィルムと断熱カーテンを併用すると効果的です。
さらに、窓枠に隙間テープを貼ることで、冷気の侵入を防げます。
このように、遮熱フィルムを使うと冬に寒くなる可能性はありますが、適切なフィルム選びや断熱対策をすれば、快適に過ごすことができます!
5.3 フィルムの寿命はどれくらい?
遮熱フィルムの寿命は約5~10年ですが、種類や環境によって異なります。
フィルムは、紫外線や気温の変化によって徐々に劣化していくため、定期的なチェックと適切なメンテナンスが大切です。
遮熱フィルムの寿命に影響する要因
フィルムの品質
高品質なフィルムは耐久性が高く、長持ちしやすい。
価格の安いフィルムは、紫外線に弱く、劣化が早いことがある。
窓の向きと紫外線の影響
南向きや西向きの窓は、紫外線が強く当たるため、フィルムの劣化が早まる傾向がある。
UVカット効果があるフィルムは、比較的長持ちしやすい。
施工の仕方とメンテナンス
きれいに貼れていないと、剥がれや気泡ができやすく、寿命が短くなることも。
正しい掃除方法で手入れをすることで、劣化を遅らせることができる。
フィルムの寿命を延ばすためのポイント
ガラスをこまめに掃除し、フィルムの汚れを取り除く
強い洗剤やアルコールを使わず、中性洗剤を薄めた水で優しく拭く
気泡や剥がれが見えたら、早めに交換を検討する
フィルムが 変色したり、剥がれてきたり、遮熱効果が感じられなくなったら交換のサイン です。適切なメンテナンスを行いながら、フィルムの効果を長持ちさせましょう!
賃貸でも剥がせるタイプの遮熱フィルムなら安心して使える
冬場は暖房熱も反射しやすいが、断熱タイプのフィルムを選べば対策可能
遮熱フィルムの寿命は約5~10年。劣化を防ぐためには適切なメンテナンスが重要
このように、遮熱フィルムに関する疑問を解決しながら、自分に合ったフィルムを選んで快適な環境を作りましょう!
▶︎6. まとめ:窓の遮熱フィルムで快適な暮らしを!
窓の遮熱フィルムは、夏の暑さ対策や紫外線カット、電気代の節約に役立つ便利なアイテムです。適切なフィルムを選び、正しく施工することで、より快適な室内環境を実現できます。
遮熱フィルムの主なメリット
室温の上昇を防ぎ、快適な空間を作る
窓からの熱の侵入を防ぐことで、室温を2~5℃下げる効果が期待できます。
エアコンの効率アップ&電気代の節約
冷房の効きが良くなり、電気代を約10~20%節約できることも。
紫外線99%以上カットで肌や家具を守る
日焼けや家具の色あせを防ぎ、長期間快適な環境を維持できます。
プライバシー保護や防犯対策にも役立つ
ミラータイプのフィルムなら、外からの視線を遮りつつ、室内の快適性を保てます。
賃貸でも使えるフィルムがある
剥がせるタイプを選べば、退去時の原状回復も安心です。
遮熱フィルムを選ぶポイント
遮熱性能の高い「反射タイプ」か、自然な仕上がりの「吸収タイプ」かを選ぶ
可視光透過率を考慮し、部屋の明るさも確保する
窓の向き(南向き・西向きなど)に適したフィルムを選ぶ
また、DIYで貼ることも可能ですが、綺麗に仕上げるにはプロの施工がおすすめ です。特に大きな窓や高所の窓は、専門業者に依頼することで耐久性の高い仕上がりになります。
遮熱フィルムで快適&エコな暮らしを!
遮熱フィルムを活用すれば、夏は涼しく、エアコンの使用を抑えながら快適な生活が送れます。また、適切なフィルムを選ぶことで、冬の寒さ対策や紫外線カットなど、年間を通して快適な住環境を実現できます。
「暑さ対策をしたい」「エアコンの効率を上げたい」「紫外線から家を守りたい」 という方は、ぜひ遮熱フィルムを活用してみてください!
▶︎窓の遮熱フィルムならトカクサポートにお任せください!
遮熱フィルムを貼ることで、暑さ対策・電気代節約・紫外線カット などの効果が期待できます。
「どのフィルムがいい?」「自分で貼るのは難しそう…」そんなお悩みはありませんか?
トカクサポートなら、プロが最適なフィルムを提案&丁寧に施工!賃貸OKのフィルムにも対応し、群馬県内で無料見積もりを実施中です。
快適な空間づくりをお手伝いします!まずはお気軽にご相談ください。



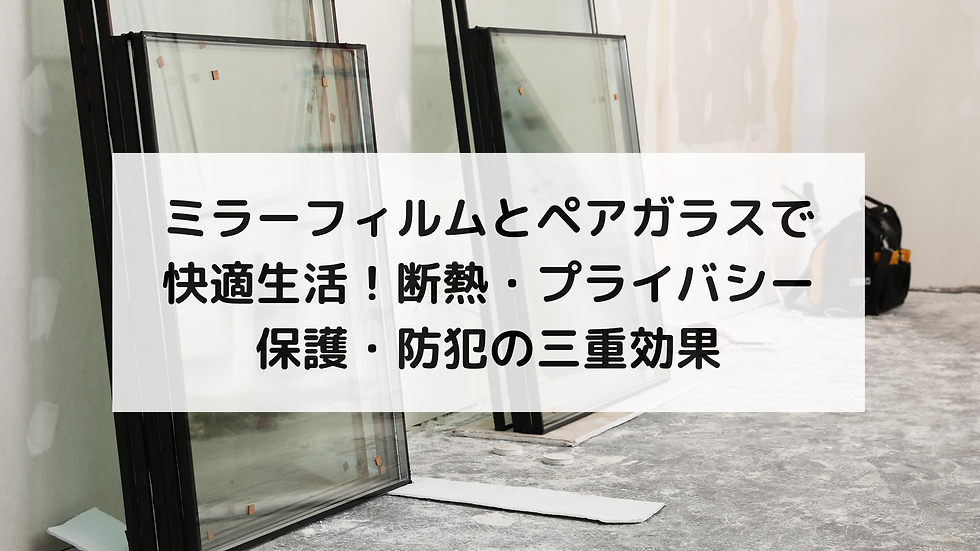
コメント